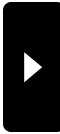2024年03月25日
2024年度 第1回 定例会報告
2024年韓国OPI研究会 第1回定例会報告書
第1回定例会の内容について以下に報告いたします。
日程 :2024年3月16日(土)14:15~17:30(14:10受付開始)
実施方法:対面(スタディカフェ【송파모임공간JUN】)+ZOOM
参加者:12名(対面3名+ZOOM9名)
内容:
14:15〜14:30 運営委員からの連絡事項
1)会長ご挨拶、年間スケジュールご案内【小島】
・定例会:第1回3月16日(土)、第2回6月予定、第3回9月予定、第4回12月予定
・在韓日本語講師会での発表:4月13日(土)15:00~にOPIの紹介とワークショップ
をする機会をいただきました(時事日本語社鐘路キャンパスとzoomの両方で
実施予定)。どなたでもご参加可能です。詳細は別途お知らせ致します。
・学会 :2025年3月未定(土曜)韓国日本語学会の企画発表で4名での発表と論文投稿
要請を会長より受けました。
→2023年に実施したプロジェクトと同様、論文査読料と論文掲載料が補助され
る予定です。
→2024年6月頃(夏休み前)を目途にプロジェクトチームを作って準備を開始
→プロジェクトの詳細は、別途ご連絡いたします。
2)会計報告、入会費・年会費について【後藤】
・2023年度会計報告→参加全員のご承認をいただきました。
・2024年度の入会費(W10,000)と年会費(w10,000)の振り込み口座ご案内
(韓国在住の会員様は国民銀行の口座へ、それ以外の会員様は日本の銀行の口座
へご入金願います)
14:30〜15:00 opiデモンストレーション(ZOOMにて)
(テスター:小島、被験者:韓国人学習者・男性・大学生)
【インタビューの流れ】
大学生→家族→趣味(野球観戦)→好きな選手の特徴→日本へ行ったこと→和牛について
→ラーメンの作り方→授業科目(歴史)について→【ロールプレイ】空港で荷物が出てこない
ので、空港職員に交渉して解決してもらえるようにする
15:00〜15:30 ◆2つのグループに分かれてレベル判定と話し合い
15:30〜16:00 ◆各グループ発表
話し合った結果、判定は3つに分かれた。それぞれの主な判定理由は
以下の通り。
・上級のどこか
複雑なものに対応していた。
・中級-上
-インタビューのやり方から判断して(トリプルパンチがなかったので)
上級ではない。
-上級の質問にうまく答えていない。質問と答えがずれている。
-上級の質問に対して中級レベルで答えている。
-上級のロールプレイも不完全(語彙が足りない)。
・中級-中
段落が出ていない。詳細の説明や発話量が不足していた。
一方で自分から話し、文章は自分で作れた。
なおインタビューの仕方で気づいた点として、以下のような意見があった。
・コミュニケーションを無視した口頭試験のような感じだった
・ロールプレイでの荷物については、カバンの特徴等の詳細についてもっ
と聞くべきだった。
16:00〜16:40 孫朱彦先生(高麗大大学院)ご発表
◆タイトル:「日本と韓国医師の疾患情報の収集戦略に関する一考察
-収集時期に焦てて-」
◆目的 :日本と韓国の医師が初診と再診において用いる言語戦略を知り
両言語の使用における様々な文化的理解を深める
◆調査方法:-分析資料は医療ドラマ20本(日本:100話分、韓国96話分)
-「医師の説話戦略類型と下位戦略」(손주언2023)を基に分析
-「専門家型」、「援助者型」、「カウンセラー型」の3つの
型別の分析
◆結果考察:1)初診においては、日韓で「専門家型」を多様していた点が共通していた。
一方で日本は「援助型」、「カウンセラー型」も少なくなかったが韓国
ではこの2つがほとんどなかった点が異なっていた。
2)再診においては「専門家型」→「カウンセラー型」→「援助型」の順に
出現することが共通していた。日本では援助型とカウンセラー型が多か
ったが、韓国では援助型が乏しかった。
3)再診においては、日本では「事実確認」の圧倒的な使用があり(治療法に
ついての)「方向設定」は出現していなかったが韓国では「方向設定」や
「治療経過確認」も少なくない使用があった。
総合的に見て、日本では相対的に相互協力的な部分をアピールする戦略が
多いと推測される。一方で韓国では身体接触などの言語以外の部分から情報
を収集することに焦点を当てている可能性があり、両者の戦略の違いが浮き
彫りになった。
16:40~17:00 質疑応答
17:00~17:30 お知らせ等
・張良光先生(在韓日本語講師会/会長)より
毎月研究発表や授業の仕方など様々なテーマで集まりをしている
(対面+ZOOMで)。どなたでも参加OKです。
→集まりの案内をいただいたらMLやカカオグループで共有します
(小島)
・小島より
-上記の在韓日本語講師会、4月13日(土)15:00~「OPI紹介&デモ」
どなたでも、対面(時事日本語社/鐘路)またはZOOMでご参加可能です。
-日本語OPI研究会(東京の研究会)メンバー主催のスタディが毎月第1日曜
に開催されており、韓国OPI研究会会員も参加可能とのこと。
→次回は4月7日(日)9:00~ZOOMにて。詳細はカカオグループで連絡い
たします。
今回はLIVEでのOPIデモンストレーションを実施しました。インタビューの仕方について何度も
確認していても、実際にやってみると不備が多く出てしまいました。日ごろから常に練習しなけれ
ばならないことを実感しました。
研究発表は孫朱彦先生の医師と患者のコミュニケーションについて、談話分析の観点から明ら
かにしたものでした。日韓の医療現場でこれほど大きな違いがあることを知って驚きました。今後
の研究の発展も楽しみです。
また今回は在韓日本語講師会の張先生と沼田先生に来ていただき、様々な情報やご意見をい
ただくことができたことも大きな収穫でした。今後、日本語教育についてより幅広い視点で活動して
いかなければならないことを実感しました。在韓日本語講師会の多彩なイベントについては、これか
ら広く共有していきたいと思いますので楽しみにしていてください。
(文責:小島堅嗣/韓国OPI研究会会長)
第1回定例会の内容について以下に報告いたします。
日程 :2024年3月16日(土)14:15~17:30(14:10受付開始)
実施方法:対面(スタディカフェ【송파모임공간JUN】)+ZOOM
参加者:12名(対面3名+ZOOM9名)
内容:
14:15〜14:30 運営委員からの連絡事項
1)会長ご挨拶、年間スケジュールご案内【小島】
・定例会:第1回3月16日(土)、第2回6月予定、第3回9月予定、第4回12月予定
・在韓日本語講師会での発表:4月13日(土)15:00~にOPIの紹介とワークショップ
をする機会をいただきました(時事日本語社鐘路キャンパスとzoomの両方で
実施予定)。どなたでもご参加可能です。詳細は別途お知らせ致します。
・学会 :2025年3月未定(土曜)韓国日本語学会の企画発表で4名での発表と論文投稿
要請を会長より受けました。
→2023年に実施したプロジェクトと同様、論文査読料と論文掲載料が補助され
る予定です。
→2024年6月頃(夏休み前)を目途にプロジェクトチームを作って準備を開始
→プロジェクトの詳細は、別途ご連絡いたします。
2)会計報告、入会費・年会費について【後藤】
・2023年度会計報告→参加全員のご承認をいただきました。
・2024年度の入会費(W10,000)と年会費(w10,000)の振り込み口座ご案内
(韓国在住の会員様は国民銀行の口座へ、それ以外の会員様は日本の銀行の口座
へご入金願います)
14:30〜15:00 opiデモンストレーション(ZOOMにて)
(テスター:小島、被験者:韓国人学習者・男性・大学生)
【インタビューの流れ】
大学生→家族→趣味(野球観戦)→好きな選手の特徴→日本へ行ったこと→和牛について
→ラーメンの作り方→授業科目(歴史)について→【ロールプレイ】空港で荷物が出てこない
ので、空港職員に交渉して解決してもらえるようにする
15:00〜15:30 ◆2つのグループに分かれてレベル判定と話し合い
15:30〜16:00 ◆各グループ発表
話し合った結果、判定は3つに分かれた。それぞれの主な判定理由は
以下の通り。
・上級のどこか
複雑なものに対応していた。
・中級-上
-インタビューのやり方から判断して(トリプルパンチがなかったので)
上級ではない。
-上級の質問にうまく答えていない。質問と答えがずれている。
-上級の質問に対して中級レベルで答えている。
-上級のロールプレイも不完全(語彙が足りない)。
・中級-中
段落が出ていない。詳細の説明や発話量が不足していた。
一方で自分から話し、文章は自分で作れた。
なおインタビューの仕方で気づいた点として、以下のような意見があった。
・コミュニケーションを無視した口頭試験のような感じだった
・ロールプレイでの荷物については、カバンの特徴等の詳細についてもっ
と聞くべきだった。
16:00〜16:40 孫朱彦先生(高麗大大学院)ご発表
◆タイトル:「日本と韓国医師の疾患情報の収集戦略に関する一考察
-収集時期に焦てて-」
◆目的 :日本と韓国の医師が初診と再診において用いる言語戦略を知り
両言語の使用における様々な文化的理解を深める
◆調査方法:-分析資料は医療ドラマ20本(日本:100話分、韓国96話分)
-「医師の説話戦略類型と下位戦略」(손주언2023)を基に分析
-「専門家型」、「援助者型」、「カウンセラー型」の3つの
型別の分析
◆結果考察:1)初診においては、日韓で「専門家型」を多様していた点が共通していた。
一方で日本は「援助型」、「カウンセラー型」も少なくなかったが韓国
ではこの2つがほとんどなかった点が異なっていた。
2)再診においては「専門家型」→「カウンセラー型」→「援助型」の順に
出現することが共通していた。日本では援助型とカウンセラー型が多か
ったが、韓国では援助型が乏しかった。
3)再診においては、日本では「事実確認」の圧倒的な使用があり(治療法に
ついての)「方向設定」は出現していなかったが韓国では「方向設定」や
「治療経過確認」も少なくない使用があった。
総合的に見て、日本では相対的に相互協力的な部分をアピールする戦略が
多いと推測される。一方で韓国では身体接触などの言語以外の部分から情報
を収集することに焦点を当てている可能性があり、両者の戦略の違いが浮き
彫りになった。
16:40~17:00 質疑応答
17:00~17:30 お知らせ等
・張良光先生(在韓日本語講師会/会長)より
毎月研究発表や授業の仕方など様々なテーマで集まりをしている
(対面+ZOOMで)。どなたでも参加OKです。
→集まりの案内をいただいたらMLやカカオグループで共有します
(小島)
・小島より
-上記の在韓日本語講師会、4月13日(土)15:00~「OPI紹介&デモ」
どなたでも、対面(時事日本語社/鐘路)またはZOOMでご参加可能です。
-日本語OPI研究会(東京の研究会)メンバー主催のスタディが毎月第1日曜
に開催されており、韓国OPI研究会会員も参加可能とのこと。
→次回は4月7日(日)9:00~ZOOMにて。詳細はカカオグループで連絡い
たします。
今回はLIVEでのOPIデモンストレーションを実施しました。インタビューの仕方について何度も
確認していても、実際にやってみると不備が多く出てしまいました。日ごろから常に練習しなけれ
ばならないことを実感しました。
研究発表は孫朱彦先生の医師と患者のコミュニケーションについて、談話分析の観点から明ら
かにしたものでした。日韓の医療現場でこれほど大きな違いがあることを知って驚きました。今後
の研究の発展も楽しみです。
また今回は在韓日本語講師会の張先生と沼田先生に来ていただき、様々な情報やご意見をい
ただくことができたことも大きな収穫でした。今後、日本語教育についてより幅広い視点で活動して
いかなければならないことを実感しました。在韓日本語講師会の多彩なイベントについては、これか
ら広く共有していきたいと思いますので楽しみにしていてください。
(文責:小島堅嗣/韓国OPI研究会会長)
Posted by J-OPI-K at
05:01
│Comments(0)
2023年12月07日
2023年度 第3回 定例会報告
2023年韓国OPI研究会 第3回定例会報告書
第3回定例会の内容について以下に報告いたします。
日程 :2023年11月25日(土)14:00~17:30(13:45受付開始)
実施方法:ZOOM
参加者:14名(うち日本語OPI研究会から2名、台湾OPI研究会から2名)
内容:
14:00〜14:10
・会長ご挨拶(小島)
・2023年度スケジュール
4月1日(土)第1回定例会
7月1日(土)第2回定例会
9月23日(土)韓国日本語学会@東国大学校ソウルキャンパス参加
→企画発表として4名(川口先生、安田先生、後藤先生、小島)が
口頭発表
11月25日(土)第3回定例会【本日】
12月 韓国日本語学会の学術誌『日本語学研究』第78号に、口頭発表
したうち3名(川口先生、安田先生、後藤先生)の投稿論文が掲載決定。
(小島の論文は今回掲載不可となったため、次号以降に再度投稿予定)
14:10〜14:40
opi音声(鮱名先生ご提供)を聞いてレベル判定&インタビューの仕方について検討
【インタビューの内容】
大学4年生、看護学専攻→専攻を選んだ理由→日本で仕事をした経験、仕事をして
よかったこと/大変だったこと→韓国と日本の福祉の違いについて→お金の有無に
よる差異について→人々の健康に対する意識について→読書について→活字離れに
ついての考え→デジタル化における文字教育について→最近気になるニュース(出
産率の低下)
14:40〜15:10
◆3つのグループに分かれてレベル判定と話し合い
15:10〜15:30
◆各グループ発表
話し合った結果、それぞれのグループで主に上級-中、上級-下、中級-上とい
う3つの判定に分かれました。主な判定理由は以下の通り。
上級-中/上級-下
・超級のタスクでは、裏付けのある意見が充分でなかった。
・上級のタスクはできていたが、安定していない部分も見られた(韓国と日本の
比較の部分)。質問と答えがかみあっていない部分も見られた。
・発音の問題があった(「看護」の発音が「観光・健康」と聞こえてしまった)。
・ロールプレイ(RP)がなかったので超級であるか否かの判断であったと思われる
が、今回のインタビューではRPが必要ではなかったか?
中級上
・文法や発音の間違いが多い。上級を維持しているかという点には疑問。
◇鮱名先生のコメント
・インタビューは以下の流れで設定した:【中級タスク】仕事について
→【上級タスク】ボランティアの詳細について→【超級トリプルパンチ1】
介護へのお金の使い方→【トリプルパンチ2】韓国の出産率について
・超級タスクは完全ではないが、かなりの部分達成できていた→上級-上と
判定。
・トリプルパンチ2の開始時間が遅かったので、もっと早い時点で
実施すべき(三浦トレーナーから指摘あり)。
15:30〜15:35 休憩
15:35〜16:40 企画発表の報告
(1)安田佳奈枝先生「OPIデータでみる韓国人学習者の外来語使用について
-過去のデータとの共通点と相違点-」
・OPIの中級レベルを対象に2013年以前のデータ(A群)、2023年
のデータ(B群)を比較
・B群がA群より高い割合で外来語を使用していた。外来語使用が
増加傾向にあることが明らかになった。
・発音の誤用と、会話を継続しようとするコミュニケーション・
ストラテジー(CS)を使用していた点は共通していた。
・本研究を通して明らかになった韓国人日本語学習者の問題点は、
1)外来語の発音、2)外来語を使用したCSのあり方、3)日韓外来語
の違いへの気づきの3点である。今後もこの3点と向き合っていく
ことを課題としたい。
(2)小島堅嗣「多言語の在韓日本語学習者におけるOPIデータの比較
-コードスイッチングの観点から-」
・研究動機
在韓日本語学習者に日本語OPIインタビューを行ったところ、複数
言語でのコードスイッチングが出現する現象があり、興味をもった。
・調査方法
OPIの超級/上級(4名)と中級(3名)それぞれにおいて、コードスイ
ッチングが現れたデータを5つの観点から(日本語/韓国語/中国語
フィラー、韓国語語彙、日本語+韓国語語彙)分析し、特徴を比較
した。
・調査結果
超級/上級グループではコードスイッチングはほぼ見られなかった
(日本語フィラーだけ出現した)。これはこのグループの日本語レベル
と日本語使用環境(日本でのビジネス経験)の影響が大きいと思われる。
中級グループでは韓国語/中国語フィラー、韓国語/韓国語+日本語
語彙によるものなど多様なコードスイッチングが出現していた。
このグループの日本語レベルによる影響がある。そのため、超級/上級
グループのような使用法を指導する必要がある。
(3)後藤歩先生「聞き手の理解度に影響を与える要素-日本語学習者の
OPIデータをもとに-」
・研究目的
1)非母語話者に慣れている/慣れていない聞き手では学習者の
発話の理解度に差異があるか、明らかにする。2)理解度に大き
影響がある「発音」の特徴について調査する。また「発音」
以外の要素についても調査する。
・調査方法
発表者が収集したOPIデータ7名分(上級-下3名、中級-上4名)
を対象とした。7名の音声をA群(韓国語を理解する日本語教師
)、B群(韓国語を理解しない日本語教師)、C群(韓国語を理解し
ない非日本語教師)に「理解しにくかった点」についてのアンケ
ート(Googleフォームによる)に答えてもらった。
・調査結果
全体的にC群の評価がA・B群の評価より高かった。どの群も
理解しにくい原因は「語彙」と「発音」が半数以上を占めた。
B・C群では「語用論的能力」を多く挙げる傾向もあったが、
上級学習者に関しては文法の間違いの影響は少なかった。
「語彙」に関しては語彙不足が最も理解を妨げる原因であること
がわかった。「発音」に関しては理解しにくい順にアクセント>
子音交替>母音交替であることがわかった。
17:00〜17:30 懇親会(情報交換会、希望者のみ)
・OPIテスター更新に関する情報交換→今後も更新についての
情報交換会を個別に行っていくことを確認
今回の定例会はまず、去年(2022年)OPIワークショップを受講後、
今年テスター資格を取得された鮱名先生に提供していただいたインタ
ビューデータを聞いて議論しました。GRID(判定表)の書き方等の情報
も得ることができて有意義でした。
次に、去る9月23日(土)に韓国日本語学会において企画発表した3名
による研究報告がありました。発表者の今後の研究にも役立てられる
ようなご質問やコメント等をいただき、ありがとうございました。
また今回は日本語OPI研究会(東京)と台湾OPI研究会の皆様も招待する
形で行われ、様々な情報交換をする時間も持つことができた貴重な機会
となりました。今後とも研究会間の交流を続けることで、OPI全体の活性
化につなげられればと考えています。来年度もよろしくお願いいたします。
(文責:小島/韓国OPI研究会会長)
第3回定例会の内容について以下に報告いたします。
日程 :2023年11月25日(土)14:00~17:30(13:45受付開始)
実施方法:ZOOM
参加者:14名(うち日本語OPI研究会から2名、台湾OPI研究会から2名)
内容:
14:00〜14:10
・会長ご挨拶(小島)
・2023年度スケジュール
4月1日(土)第1回定例会
7月1日(土)第2回定例会
9月23日(土)韓国日本語学会@東国大学校ソウルキャンパス参加
→企画発表として4名(川口先生、安田先生、後藤先生、小島)が
口頭発表
11月25日(土)第3回定例会【本日】
12月 韓国日本語学会の学術誌『日本語学研究』第78号に、口頭発表
したうち3名(川口先生、安田先生、後藤先生)の投稿論文が掲載決定。
(小島の論文は今回掲載不可となったため、次号以降に再度投稿予定)
14:10〜14:40
opi音声(鮱名先生ご提供)を聞いてレベル判定&インタビューの仕方について検討
【インタビューの内容】
大学4年生、看護学専攻→専攻を選んだ理由→日本で仕事をした経験、仕事をして
よかったこと/大変だったこと→韓国と日本の福祉の違いについて→お金の有無に
よる差異について→人々の健康に対する意識について→読書について→活字離れに
ついての考え→デジタル化における文字教育について→最近気になるニュース(出
産率の低下)
14:40〜15:10
◆3つのグループに分かれてレベル判定と話し合い
15:10〜15:30
◆各グループ発表
話し合った結果、それぞれのグループで主に上級-中、上級-下、中級-上とい
う3つの判定に分かれました。主な判定理由は以下の通り。
上級-中/上級-下
・超級のタスクでは、裏付けのある意見が充分でなかった。
・上級のタスクはできていたが、安定していない部分も見られた(韓国と日本の
比較の部分)。質問と答えがかみあっていない部分も見られた。
・発音の問題があった(「看護」の発音が「観光・健康」と聞こえてしまった)。
・ロールプレイ(RP)がなかったので超級であるか否かの判断であったと思われる
が、今回のインタビューではRPが必要ではなかったか?
中級上
・文法や発音の間違いが多い。上級を維持しているかという点には疑問。
◇鮱名先生のコメント
・インタビューは以下の流れで設定した:【中級タスク】仕事について
→【上級タスク】ボランティアの詳細について→【超級トリプルパンチ1】
介護へのお金の使い方→【トリプルパンチ2】韓国の出産率について
・超級タスクは完全ではないが、かなりの部分達成できていた→上級-上と
判定。
・トリプルパンチ2の開始時間が遅かったので、もっと早い時点で
実施すべき(三浦トレーナーから指摘あり)。
15:30〜15:35 休憩
15:35〜16:40 企画発表の報告
(1)安田佳奈枝先生「OPIデータでみる韓国人学習者の外来語使用について
-過去のデータとの共通点と相違点-」
・OPIの中級レベルを対象に2013年以前のデータ(A群)、2023年
のデータ(B群)を比較
・B群がA群より高い割合で外来語を使用していた。外来語使用が
増加傾向にあることが明らかになった。
・発音の誤用と、会話を継続しようとするコミュニケーション・
ストラテジー(CS)を使用していた点は共通していた。
・本研究を通して明らかになった韓国人日本語学習者の問題点は、
1)外来語の発音、2)外来語を使用したCSのあり方、3)日韓外来語
の違いへの気づきの3点である。今後もこの3点と向き合っていく
ことを課題としたい。
(2)小島堅嗣「多言語の在韓日本語学習者におけるOPIデータの比較
-コードスイッチングの観点から-」
・研究動機
在韓日本語学習者に日本語OPIインタビューを行ったところ、複数
言語でのコードスイッチングが出現する現象があり、興味をもった。
・調査方法
OPIの超級/上級(4名)と中級(3名)それぞれにおいて、コードスイ
ッチングが現れたデータを5つの観点から(日本語/韓国語/中国語
フィラー、韓国語語彙、日本語+韓国語語彙)分析し、特徴を比較
した。
・調査結果
超級/上級グループではコードスイッチングはほぼ見られなかった
(日本語フィラーだけ出現した)。これはこのグループの日本語レベル
と日本語使用環境(日本でのビジネス経験)の影響が大きいと思われる。
中級グループでは韓国語/中国語フィラー、韓国語/韓国語+日本語
語彙によるものなど多様なコードスイッチングが出現していた。
このグループの日本語レベルによる影響がある。そのため、超級/上級
グループのような使用法を指導する必要がある。
(3)後藤歩先生「聞き手の理解度に影響を与える要素-日本語学習者の
OPIデータをもとに-」
・研究目的
1)非母語話者に慣れている/慣れていない聞き手では学習者の
発話の理解度に差異があるか、明らかにする。2)理解度に大き
影響がある「発音」の特徴について調査する。また「発音」
以外の要素についても調査する。
・調査方法
発表者が収集したOPIデータ7名分(上級-下3名、中級-上4名)
を対象とした。7名の音声をA群(韓国語を理解する日本語教師
)、B群(韓国語を理解しない日本語教師)、C群(韓国語を理解し
ない非日本語教師)に「理解しにくかった点」についてのアンケ
ート(Googleフォームによる)に答えてもらった。
・調査結果
全体的にC群の評価がA・B群の評価より高かった。どの群も
理解しにくい原因は「語彙」と「発音」が半数以上を占めた。
B・C群では「語用論的能力」を多く挙げる傾向もあったが、
上級学習者に関しては文法の間違いの影響は少なかった。
「語彙」に関しては語彙不足が最も理解を妨げる原因であること
がわかった。「発音」に関しては理解しにくい順にアクセント>
子音交替>母音交替であることがわかった。
17:00〜17:30 懇親会(情報交換会、希望者のみ)
・OPIテスター更新に関する情報交換→今後も更新についての
情報交換会を個別に行っていくことを確認
今回の定例会はまず、去年(2022年)OPIワークショップを受講後、
今年テスター資格を取得された鮱名先生に提供していただいたインタ
ビューデータを聞いて議論しました。GRID(判定表)の書き方等の情報
も得ることができて有意義でした。
次に、去る9月23日(土)に韓国日本語学会において企画発表した3名
による研究報告がありました。発表者の今後の研究にも役立てられる
ようなご質問やコメント等をいただき、ありがとうございました。
また今回は日本語OPI研究会(東京)と台湾OPI研究会の皆様も招待する
形で行われ、様々な情報交換をする時間も持つことができた貴重な機会
となりました。今後とも研究会間の交流を続けることで、OPI全体の活性
化につなげられればと考えています。来年度もよろしくお願いいたします。
(文責:小島/韓国OPI研究会会長)
Posted by J-OPI-K at
08:44
│Comments(0)
2023年07月05日
2023年度第2回定例会 報告書
第2回定例会の内容について以下に報告いたします。
日程 :2023年7月1日(土)14:00~17:25(13:45受付開始)
実施方法:ZOOM
参加者:15名(うち台湾OPI研究会から6名)
内容:
14:00〜14:30
会長ご挨拶、台湾OPI研究会様ご紹介【小島】
2)韓国OPI研究会の活動について【小島】
・国際交流基金のデータによると、2021年は3年前(2018年)よりも高等教育における
日本語学習者の比率が高まっている。→大学において本格的に日本語を学び、日本での
就職につなげたい学習者が増加していると推測される。
・2022年度ワークショップを受けたメンバーが資格取得を目指し、OPIインタビューを
収録している段階。
14:30〜15:05 opi音声(安田先生ご提供)を聞いて、以下の3点について考える。
〈1〉レベル判定、〈2〉判定理由、〈3〉外来語の語彙が多く出現している
ことについての分析
【インタビューの内容】
大学1年生→今住んでいるところ→入りたいサークル→日本のアイドルについ
て→学生寮の生活→コロナのときの授業→コロナ後に変わったこと→ロールプ
レイ(空港で荷物が出ないので、職員に問い合わせる)
15:05〜15:15 (休憩)
15:15〜15:45 ◆3つのグループに分かれてレベル判定と話し合い
15:45〜16:00 ◆各グループ発表
話し合った結果、それぞれのグループで初級上、中級下、中級中という3つ
の判定に分かれた。主な判定理由は以下の通り。
初級上
・文のレベルの発話が見られたが、維持はしていない。
・単語がわからなかったり、文のしめくくりができていない部分があった
中級下
・文の質がよくない(文法活用、テンスアスペクト)
中級中
・文のレベルで話している。そして上級のタスクは一部できていた。
・比較等、上級の突き上げができていなかった。被験者にとって難しい
内容であった。
なお、インタビューを聞いて気づいた部分、および外来語語彙について以下の
点が指摘された。
・話題が学校のことに偏っていた。
・テスターが単語を教えたり、内容をまとめたりしていた。
・ロールプレイが上級のものを使用していた理由、何がねらいだったかという
部分が知りたい。タスクも上級のものが多かったが、中級のタスクをしっか
りすべき。
・外来語使用は「代替ストラテジー」と思われる←チョイス、ステア等
研究会としての判定結果(有資格者2名で判定)は「初級上」となった。理由は
以下の通り。
・単語レベルで十分に答えられていた一方、文レベルは維持していなかった
→被験者自ら「すみません!」と挫折している箇所が複数見られた。
・中級の質問をもっと多くして、中級がどのくらいできるか見極められると
よかった。
・ロールプレイも中級のものを実施するのがよい。
・マニュアルp.61における「初級-上」の記述の「主に現在形の短い文、時には
不完全な複数の文で構成される」、「発話は躊躇が見られ、間違いを含んで
いることもある」、「理解可能な文で答えられることもあるが、文レベルの
発話を維持することはできない」という特徴にもっともよく当てはまっている。
16:00〜17:00 台湾opi研究会様 ご発表
(1)台湾における日本語教育について【澤田先生、GU先生、陳先生、許先生】
・国際交流基金のデータによると、台湾の日本語学習者の規模は韓国の1/3
程度である。日本関連の科目があるのは139機関、大学では日本学科が48校
に設置されている。(国立等の大学は「日本学科」という名称が多いが、比較
的新しい私立大学でビジネス・観光等に力を入れている大学では「応用日本語
学科」となっているところが多い)。
・台湾教育部が2019年に小中高12年の新しい学習要領を策定した。
・第二外国語は学校の裁量に任せられてる(放課後のクラブ活動など)一番人気な
のは日本語で、二番目が韓国語である。
・公立中学の選択授業で日本語授業がある(学生に人気がある)。
・台湾での日本語学習の動機は1.卒業要件(大学:N1、商業高校:n5等)、2.日
本への旅行で役立てたいという理由が多い。
・「社区大学」という地域の学校が1999年に設立され、日本語に関する様々な
コースを開設している(日本の歌、『みんなの日本語』を使った授業)。
・台湾の大学生が日本就職の準備として、インターンシップ等に参加することが
ある(以前から行われている)。国としても日本に送り出す機会や交流の機会を
作っている。
(2)台湾OPI研究会の活動について【GU先生】
・現在のメンバーは10名ほど
・2015年のOPI函館国際大会のときに設立された(次回の国際大会が
台湾に決定したことがきっかけとなった)
・2017年1月、嶋田先生によるプレイベントを開催(淡江大学)
・2017年8月、opi台湾国際大会を開催(淡江大学)→その後、活動は下火
になる
・2019年9月、研究会の活動が再開される←テスター更新の先生が再度
集まったのがきっかけ
・コロナの時期に活動が停滞していたが、現在は徐々に復活しており、
2020年からは勉強会を行っている(関連の本を読む、音声を聞いてレベル
判定等)
17:00〜17:30 懇親会(情報交換会、希望者のみ)
様々な意見が出たが、主要な事柄は以下の2点。
・今後とも、韓国と台湾を含めOPI研究会の協同を進めていきたいという
考えで一致。
・台湾OPI研究会からは、テスター資格更新に関する最新情報を共有して
もらえる機会を作ってほしいという要望が出た。
今回の定例会は台湾OPI研究会の先生方も招待する形で開かれました。これは以前に別の学会で韓国にいらっしゃっていた、国立台中科技大学の羅暁勤先生との交流の中で実現したものでした。今回は様々な方が意見を出し合い、活発な情報交換ができました。台湾・韓国のメンバーがお互いにとってとても有意義な会になったと確信しています。また韓国在住の私たちにとって台湾の日本語教育の情報に接することはとても少ないので、澤田先生、Gu先生、陳先生、許先生のお話もお聞きできて、さらに多くの時間を割いて質問にお答えいただけたことはとても貴重な機会となりました。今後も台湾OPI研究会様との交流をさらに様々な形で広げていきたいと考えています。これからもいろいろなアイデアをもとに定例会やその他の企画をしていきたいと思いますので、皆様がお持ちのアイデアがありましたらぜひお寄せください。
(文責:小島/韓国OPI研究会会長)
日程 :2023年7月1日(土)14:00~17:25(13:45受付開始)
実施方法:ZOOM
参加者:15名(うち台湾OPI研究会から6名)
内容:
14:00〜14:30
会長ご挨拶、台湾OPI研究会様ご紹介【小島】
2)韓国OPI研究会の活動について【小島】
・国際交流基金のデータによると、2021年は3年前(2018年)よりも高等教育における
日本語学習者の比率が高まっている。→大学において本格的に日本語を学び、日本での
就職につなげたい学習者が増加していると推測される。
・2022年度ワークショップを受けたメンバーが資格取得を目指し、OPIインタビューを
収録している段階。
14:30〜15:05 opi音声(安田先生ご提供)を聞いて、以下の3点について考える。
〈1〉レベル判定、〈2〉判定理由、〈3〉外来語の語彙が多く出現している
ことについての分析
【インタビューの内容】
大学1年生→今住んでいるところ→入りたいサークル→日本のアイドルについ
て→学生寮の生活→コロナのときの授業→コロナ後に変わったこと→ロールプ
レイ(空港で荷物が出ないので、職員に問い合わせる)
15:05〜15:15 (休憩)
15:15〜15:45 ◆3つのグループに分かれてレベル判定と話し合い
15:45〜16:00 ◆各グループ発表
話し合った結果、それぞれのグループで初級上、中級下、中級中という3つ
の判定に分かれた。主な判定理由は以下の通り。
初級上
・文のレベルの発話が見られたが、維持はしていない。
・単語がわからなかったり、文のしめくくりができていない部分があった
中級下
・文の質がよくない(文法活用、テンスアスペクト)
中級中
・文のレベルで話している。そして上級のタスクは一部できていた。
・比較等、上級の突き上げができていなかった。被験者にとって難しい
内容であった。
なお、インタビューを聞いて気づいた部分、および外来語語彙について以下の
点が指摘された。
・話題が学校のことに偏っていた。
・テスターが単語を教えたり、内容をまとめたりしていた。
・ロールプレイが上級のものを使用していた理由、何がねらいだったかという
部分が知りたい。タスクも上級のものが多かったが、中級のタスクをしっか
りすべき。
・外来語使用は「代替ストラテジー」と思われる←チョイス、ステア等
研究会としての判定結果(有資格者2名で判定)は「初級上」となった。理由は
以下の通り。
・単語レベルで十分に答えられていた一方、文レベルは維持していなかった
→被験者自ら「すみません!」と挫折している箇所が複数見られた。
・中級の質問をもっと多くして、中級がどのくらいできるか見極められると
よかった。
・ロールプレイも中級のものを実施するのがよい。
・マニュアルp.61における「初級-上」の記述の「主に現在形の短い文、時には
不完全な複数の文で構成される」、「発話は躊躇が見られ、間違いを含んで
いることもある」、「理解可能な文で答えられることもあるが、文レベルの
発話を維持することはできない」という特徴にもっともよく当てはまっている。
16:00〜17:00 台湾opi研究会様 ご発表
(1)台湾における日本語教育について【澤田先生、GU先生、陳先生、許先生】
・国際交流基金のデータによると、台湾の日本語学習者の規模は韓国の1/3
程度である。日本関連の科目があるのは139機関、大学では日本学科が48校
に設置されている。(国立等の大学は「日本学科」という名称が多いが、比較
的新しい私立大学でビジネス・観光等に力を入れている大学では「応用日本語
学科」となっているところが多い)。
・台湾教育部が2019年に小中高12年の新しい学習要領を策定した。
・第二外国語は学校の裁量に任せられてる(放課後のクラブ活動など)一番人気な
のは日本語で、二番目が韓国語である。
・公立中学の選択授業で日本語授業がある(学生に人気がある)。
・台湾での日本語学習の動機は1.卒業要件(大学:N1、商業高校:n5等)、2.日
本への旅行で役立てたいという理由が多い。
・「社区大学」という地域の学校が1999年に設立され、日本語に関する様々な
コースを開設している(日本の歌、『みんなの日本語』を使った授業)。
・台湾の大学生が日本就職の準備として、インターンシップ等に参加することが
ある(以前から行われている)。国としても日本に送り出す機会や交流の機会を
作っている。
(2)台湾OPI研究会の活動について【GU先生】
・現在のメンバーは10名ほど
・2015年のOPI函館国際大会のときに設立された(次回の国際大会が
台湾に決定したことがきっかけとなった)
・2017年1月、嶋田先生によるプレイベントを開催(淡江大学)
・2017年8月、opi台湾国際大会を開催(淡江大学)→その後、活動は下火
になる
・2019年9月、研究会の活動が再開される←テスター更新の先生が再度
集まったのがきっかけ
・コロナの時期に活動が停滞していたが、現在は徐々に復活しており、
2020年からは勉強会を行っている(関連の本を読む、音声を聞いてレベル
判定等)
17:00〜17:30 懇親会(情報交換会、希望者のみ)
様々な意見が出たが、主要な事柄は以下の2点。
・今後とも、韓国と台湾を含めOPI研究会の協同を進めていきたいという
考えで一致。
・台湾OPI研究会からは、テスター資格更新に関する最新情報を共有して
もらえる機会を作ってほしいという要望が出た。
今回の定例会は台湾OPI研究会の先生方も招待する形で開かれました。これは以前に別の学会で韓国にいらっしゃっていた、国立台中科技大学の羅暁勤先生との交流の中で実現したものでした。今回は様々な方が意見を出し合い、活発な情報交換ができました。台湾・韓国のメンバーがお互いにとってとても有意義な会になったと確信しています。また韓国在住の私たちにとって台湾の日本語教育の情報に接することはとても少ないので、澤田先生、Gu先生、陳先生、許先生のお話もお聞きできて、さらに多くの時間を割いて質問にお答えいただけたことはとても貴重な機会となりました。今後も台湾OPI研究会様との交流をさらに様々な形で広げていきたいと考えています。これからもいろいろなアイデアをもとに定例会やその他の企画をしていきたいと思いますので、皆様がお持ちのアイデアがありましたらぜひお寄せください。
(文責:小島/韓国OPI研究会会長)
Posted by J-OPI-K at
10:09
│Comments(0)
2023年04月10日
2023年度 第1回 定例会報告
2023年韓国OPI研究会 第1回定例会報告書
第1回定例会の内容について以下に報告いたします。
日程 :2023年4月1日(土)14:15~16:50(14:05受付開始)
実施方法:対面(スタディカフェ【Early Bird반포점】)+ZOOM
参加者:15名(対面7名+ZOOM8名)
内容:
14:15〜14:30 運営委員からの連絡事項
1)会長ご挨拶、年間スケジュールご案内【小島】
・定例会:第1回4月1日(土)、第2回6月予定、第3回9月予定、第4回12月予定
・学会 :4月23日(土)韓国日本語教育学会の企画発表にて4名発表予定
・スタディ:ワークショップ15期生を中心に不定期で実施中(ZOOMにて)
2)会計報告、入会費・年会費について【後藤】
・2022年度会計報告→参加全員のご承認をいただきました。
・2023年度の入会費(W10,000)と年会費(w10,000)の振り込み口座ご案内
(韓国在住の会員様は国民銀行の口座へ、それ以外の会員様は日本の銀行の口座へご入金
願います)
14:30〜15:00 opiデモンストレーション(ZOOMにて)
(テスター:迫田先生、被験者:韓国人学習者・男性・大学生)
【インタビューの流れ】
大学4年生→冬休みにしたこと(TOEIC勉強)→アルバイト→大学4年で
ワンルームに引っ越した理由→部屋の契約→一人暮らしで難しいこと
→実家暮らしと一人暮らしの比較→孤独死について→アルバイトの内容を
詳しく説明(コンビニの接客、商品補充、料理、清掃)→アルバイトで大変
だったこと(酔っぱらったお客が来て、警察を呼んだ)→お客の立場に立って
考える→このような問題に対して韓国社会はどう対応すべきか
15:00〜15:35 ◆3つのグループに分かれてレベル判定と話し合い
15:35〜15:40 (休憩)
15:40〜16:15 ◆各グループ発表
話し合った結果、それぞれのグループで中級上と上級下という2つの判定
に分かれた。主な判定理由は以下の通り。
中級上
・中級のタスクは軽々こなしていた
・語彙が足りないので、段落が難しい部分があった
・描写ができていない
・時制のコントロールができていない部分があった
・超級のタスクができていない
・聞き手に理解できない語彙があった(例:「じゅく」→寄宿舎のこと)
・「文の羅列」の部分が多い
上級下
・ナラティブ(語り)が安定しており、比較もできていた
・超級のタスクの内容が聞き取れていて、答えも的はずれではなかった
なお、インタビューを聞いて気づいた部分として以下の点が指摘された。
・テスターが被験者を助けてしまう場面が多くみられた(テスターが言い換え
たり、まとめてしまっていた)
・ロールプレイの設定(先生と学生、学生同士など)をもう少し厳密にした
ほうがよい(今回は借りたアイパッドをなくしたことに対して、コーヒーを
おごったら許す、という展開になっていた)
・上級のロールプレイでは、出来事の経緯や解決方法等に関する「交渉」
の部分をしっかり提示すべき
最終的な判定結果については、研究会の複数の有資格者で再度検討したのち
決定し、別途報告いたします。
16:15〜16:50 樋口先生ご発表
◆タイトル:「JLPT対策を中心に学習をしてきた韓国人留学生の日本語学習に必要なものに対する意識について
~入国前と入国後を比較
して」
◆目的 :1)韓国人留学生日本語学習に何が必要か、また何を準備しておくとよいか→大学入学前と入学1年目の学生の比較
2)大学で使用するための日本語に対し、韓国の教師の授業に
望むこと
◆調査期間:2023年3月23日~3月28日
◆調査対象と調査方法
:K大学(理工系)韓国人留学生、新1年生/新2年生
→Google FORMSを用いてアンケートを実施した
◆調査結果:・大学で必要な日本語は入学前、入学後ともに①用語・単語・
言葉、②聞き取りの2点であった。
・大学の授業で必要な日本語について在韓中に準備しておく
ものは全員が「用語・単語・ことば・語彙力・漢字」を
挙げた。
・日本の生活で必要な日本語については入国後学生が「対話のための会話・トラブルの解決」を挙げ、入国前学生は具体的なイメージをもっていないことがわかった。
・日本での生活で必要な日本語について在韓中に準備しておくものについて入国後学生は「ドラマ・Youtube・動画等の、
状況設定がある媒体」を挙げ、入国前学生は様々な勉強方法
を挙げていて一致しなかった。
・日本に来て日本語がうまく使えず困った場面について入学後
学生は「記述テストの出題意図が理解できない」と述べた。
・韓国で日本語を教える教師に望むことについて入学後学生から「漢字指導」を全員が挙げた一方で「友達言葉、流行語」、「発音を直す」は0名であった。
◆考察 :1)大学で必要なものについて共通していたのは「語彙力」。
2)生活で必要な日本語では「動画や状況がはっきりしている」「対話やタスク、伝えたいことが作り出せる」資料が
要望されている。
3)韓国の教師の指導や授業に望むものは「漢字指導」。
16:50 終了
今回の定例会はドイツから一時帰国中にご参加の先生を含めて7名の対面参加者、ZOOMでは初参加の先生も含めて8名のご参加でした。
デモンストレーションのレベル判定に関する話し合いは白熱するほど活発な意見交換がなされました。また樋口先生のご発表では、日本在住
の韓国人学習者の語彙習得に関する課題が提出され、現場で起きている問題点を私たちみんなで考えなければならないということを実感
しました。
今年は9月23日(土)に協力学会である韓国日本語学会での発表や、その後の論文投稿(12月の学術誌に掲載予定)をするプロジェクトを控えています。現在このプロジェクトに向けて少しずつ準備を進めているところです。これらの活動も含め、研究会の活動に関心をもっていただける先生方が増えていけば幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。
(文責:小島/韓国OPI研究会会長)
第1回定例会の内容について以下に報告いたします。
日程 :2023年4月1日(土)14:15~16:50(14:05受付開始)
実施方法:対面(スタディカフェ【Early Bird반포점】)+ZOOM
参加者:15名(対面7名+ZOOM8名)
内容:
14:15〜14:30 運営委員からの連絡事項
1)会長ご挨拶、年間スケジュールご案内【小島】
・定例会:第1回4月1日(土)、第2回6月予定、第3回9月予定、第4回12月予定
・学会 :4月23日(土)韓国日本語教育学会の企画発表にて4名発表予定
・スタディ:ワークショップ15期生を中心に不定期で実施中(ZOOMにて)
2)会計報告、入会費・年会費について【後藤】
・2022年度会計報告→参加全員のご承認をいただきました。
・2023年度の入会費(W10,000)と年会費(w10,000)の振り込み口座ご案内
(韓国在住の会員様は国民銀行の口座へ、それ以外の会員様は日本の銀行の口座へご入金
願います)
14:30〜15:00 opiデモンストレーション(ZOOMにて)
(テスター:迫田先生、被験者:韓国人学習者・男性・大学生)
【インタビューの流れ】
大学4年生→冬休みにしたこと(TOEIC勉強)→アルバイト→大学4年で
ワンルームに引っ越した理由→部屋の契約→一人暮らしで難しいこと
→実家暮らしと一人暮らしの比較→孤独死について→アルバイトの内容を
詳しく説明(コンビニの接客、商品補充、料理、清掃)→アルバイトで大変
だったこと(酔っぱらったお客が来て、警察を呼んだ)→お客の立場に立って
考える→このような問題に対して韓国社会はどう対応すべきか
15:00〜15:35 ◆3つのグループに分かれてレベル判定と話し合い
15:35〜15:40 (休憩)
15:40〜16:15 ◆各グループ発表
話し合った結果、それぞれのグループで中級上と上級下という2つの判定
に分かれた。主な判定理由は以下の通り。
中級上
・中級のタスクは軽々こなしていた
・語彙が足りないので、段落が難しい部分があった
・描写ができていない
・時制のコントロールができていない部分があった
・超級のタスクができていない
・聞き手に理解できない語彙があった(例:「じゅく」→寄宿舎のこと)
・「文の羅列」の部分が多い
上級下
・ナラティブ(語り)が安定しており、比較もできていた
・超級のタスクの内容が聞き取れていて、答えも的はずれではなかった
なお、インタビューを聞いて気づいた部分として以下の点が指摘された。
・テスターが被験者を助けてしまう場面が多くみられた(テスターが言い換え
たり、まとめてしまっていた)
・ロールプレイの設定(先生と学生、学生同士など)をもう少し厳密にした
ほうがよい(今回は借りたアイパッドをなくしたことに対して、コーヒーを
おごったら許す、という展開になっていた)
・上級のロールプレイでは、出来事の経緯や解決方法等に関する「交渉」
の部分をしっかり提示すべき
最終的な判定結果については、研究会の複数の有資格者で再度検討したのち
決定し、別途報告いたします。
16:15〜16:50 樋口先生ご発表
◆タイトル:「JLPT対策を中心に学習をしてきた韓国人留学生の日本語学習に必要なものに対する意識について
~入国前と入国後を比較
して」
◆目的 :1)韓国人留学生日本語学習に何が必要か、また何を準備しておくとよいか→大学入学前と入学1年目の学生の比較
2)大学で使用するための日本語に対し、韓国の教師の授業に
望むこと
◆調査期間:2023年3月23日~3月28日
◆調査対象と調査方法
:K大学(理工系)韓国人留学生、新1年生/新2年生
→Google FORMSを用いてアンケートを実施した
◆調査結果:・大学で必要な日本語は入学前、入学後ともに①用語・単語・
言葉、②聞き取りの2点であった。
・大学の授業で必要な日本語について在韓中に準備しておく
ものは全員が「用語・単語・ことば・語彙力・漢字」を
挙げた。
・日本の生活で必要な日本語については入国後学生が「対話のための会話・トラブルの解決」を挙げ、入国前学生は具体的なイメージをもっていないことがわかった。
・日本での生活で必要な日本語について在韓中に準備しておくものについて入国後学生は「ドラマ・Youtube・動画等の、
状況設定がある媒体」を挙げ、入国前学生は様々な勉強方法
を挙げていて一致しなかった。
・日本に来て日本語がうまく使えず困った場面について入学後
学生は「記述テストの出題意図が理解できない」と述べた。
・韓国で日本語を教える教師に望むことについて入学後学生から「漢字指導」を全員が挙げた一方で「友達言葉、流行語」、「発音を直す」は0名であった。
◆考察 :1)大学で必要なものについて共通していたのは「語彙力」。
2)生活で必要な日本語では「動画や状況がはっきりしている」「対話やタスク、伝えたいことが作り出せる」資料が
要望されている。
3)韓国の教師の指導や授業に望むものは「漢字指導」。
16:50 終了
今回の定例会はドイツから一時帰国中にご参加の先生を含めて7名の対面参加者、ZOOMでは初参加の先生も含めて8名のご参加でした。
デモンストレーションのレベル判定に関する話し合いは白熱するほど活発な意見交換がなされました。また樋口先生のご発表では、日本在住
の韓国人学習者の語彙習得に関する課題が提出され、現場で起きている問題点を私たちみんなで考えなければならないということを実感
しました。
今年は9月23日(土)に協力学会である韓国日本語学会での発表や、その後の論文投稿(12月の学術誌に掲載予定)をするプロジェクトを控えています。現在このプロジェクトに向けて少しずつ準備を進めているところです。これらの活動も含め、研究会の活動に関心をもっていただける先生方が増えていけば幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。
(文責:小島/韓国OPI研究会会長)
Posted by J-OPI-K at
06:17
│Comments(0)
2022年12月20日
2022年度 第4回 韓国OPI研究会 定例会報告
2022年韓国OPI研究会 第4回定例会報告書
第4回定例会の内容について以下に報告いたします。
日程 :2022年12月10日(土)14:15~17:45(14:05受付開始)
実施方法:対面(スタディカフェ구겐하임〈大邱〉)とオンライン(ZOOM)
参加者:16名(対面4名、オンライン12名〈うち、デモの被験者2名〉)
内容:
14:15〜14:30 会長ご挨拶、年間スケジュールご案内(小島)
・今回招待させていただいた、日本語OPI研究会のケッチャム会長、世良前会長
からのご挨拶
・2023年度のスケジュール
-1月下旬から2月中旬に研究プロジェクト募集→別途MLにて募集をします。
→2月末に採用研究を発表、3月に助成金を支給
-定例会開催予定:3月、6月、10月、12月の土曜日
-提携学会である韓国日本語教育学会より、発表と論文でのOPI特集を組んでいただけ
るとのご提案あり。5件(5名)の学会発表と論文投稿→9月に発表と論文投稿、学術誌掲載は12月。
→詳細は、別途MLにて募集をします。
14:30〜15:00 OPIデモンストレーション1
(テスター:今井先生、被験者:韓国人日本語学習者、大学生)
【インタビューの流れ】
故郷のチャンウォンについて(I)→専攻しているパーツデザインの設計に
ついて(A)→自動運転システムについて(S)→自動運転の危険性についての
意見(S)→今後、自動車はどのように発展していくか?(S)→ランニングに
ついて(I)→やせる以外の効果について(A/S)→ロールプレイ〈友達がSNS
に中傷を書いていたので、抗議してやめさせる〉(A)
15:00~15:30 3グループに分かれて議論(レベル判定、インタビューの仕方について)
15:30〜15:35 (休憩)
15:35〜15:55 各グループ発表
中級と上級の2つの結果に分かれた。それぞれの判定の主な理由は以下の通り。
中級-上
・しっかりした上級のタスク(叙述、比較)が少なかった。
・発話が文の羅列になっており、段落が構成されていない部分があった。
・発話内容が聞き手にとって理解しにくかった。
上級-下/中
・つっこんだ質問やナラティブ(語り)の質問がなかった。
・トリプルパンチの質問に対して被験者が逃げてしまう部分があった。
→超級×
また、インタビューの仕方に関するコメントも挙げられた。
・インタビューの全体の流れはとてもよかった。
・ウォーミングアップの時間をもう少し長くとり、様々な話題を集める
ようにするといいのではないか。
・被験者の意見をテスターがまとめてしまう部分が見られた。
《研究会としての判定(テスター保持者2名による判定)》
レベル:上級-中
判定理由:
・多数のコミュニカティブタスクを容易に自信をもってこなした。
・つながりのある段落の長さで、関連性のある事実を伝えられた。
・超級レベルをこなすときに、量と質の両方において発話レベル
が低下していた。
・超級タスクである仮説、反論に対する答えができていない。
→ほぼ超級=上級-上のところまでは達していない
15:55〜16:25 OPIデモンストレーション2
(テスター:鮱名先生、被験者:韓国人日本語学習者、会社員)
【インタビューの流れ】
家族、居住地のヨンインについて(I)→会社の業務内容(A)→会社での問題(S)
→イテウォンの事故について(A)→その際の警察の責任について(S)→安全に
関する個人の意識はどう変わるか(S)→映画「オジンオゲーム」について (A)
→ロールプレイ:運転免許の書き換えについて交渉(A)。
16:25~16:35 (休憩)
16:35~17:05 3グループに分かれて議論(レベル判定、インタビューの仕方について)
17:05~17:20 各グループ発表
中級と上級の2つの結果に分かれた。それぞれの判定の主な理由は以下の
通り。
中級-上
・叙述や描写の部分で挫折がみられた。
・段落が構成させていない部分、文の羅列があった。
・質問に対する答えがずれている部分があった。
・ロールプレイの内容が理解できていないようだった。
・韓国語由来の語彙を日本語で説明できていない部分があった。
→「ぎょうじ」、「ボキ」
上級-中
・発話量が多く、上級タスクもこなせていた。
インタビューのやり方についての意見
・インタビューの流れがスムーズでよかった。
・ 質問がスムーズにできていた。
《研究会としての判定(テスター保持者2名による判定)》
レベル:中級-上
判定理由
・中級レベルでの日常的によく起こるタスクや社交的場面を扱う際に
容易に自信を持ってやりとりができていた。
・かなりの数の上級タスクが遂行できていたが、できていない部分も
あった(映画のストーリー)→上級を維持していない。
17:45 終了
今回の定例会も、対面とオンラインの両方で開催しました。今回は日本語OPI研究会(東京)のケッチャム現会長と
世良前会長に出席していただき、一緒にOPIのレベル判定をしていただきました。そして今回の定例会のために、
小池先生、孫先生のご協力で2人の被験者に協力してもらうことができ、LIVEでのデモンストレーションを2件行う
ことができました。このような貴重な機会を作ることができたのも、両先生を始め会員の皆様のご協力で成り立って
いることに、改めて感謝いたします。
来年度(2023年度)は提携学会での学会発表や論文投稿といった研究の面でも力を注いでいく1年になると思いますが、
実際のOPIを実践したりレベル判定したりする機会もさらに増やしていきたいと考えています。来年度も皆様と一緒に
活動していければと思いますので、宜しくお願いいたします。
(文責:小島堅嗣/韓国OPI研究会会長)
第4回定例会の内容について以下に報告いたします。
日程 :2022年12月10日(土)14:15~17:45(14:05受付開始)
実施方法:対面(スタディカフェ구겐하임〈大邱〉)とオンライン(ZOOM)
参加者:16名(対面4名、オンライン12名〈うち、デモの被験者2名〉)
内容:
14:15〜14:30 会長ご挨拶、年間スケジュールご案内(小島)
・今回招待させていただいた、日本語OPI研究会のケッチャム会長、世良前会長
からのご挨拶
・2023年度のスケジュール
-1月下旬から2月中旬に研究プロジェクト募集→別途MLにて募集をします。
→2月末に採用研究を発表、3月に助成金を支給
-定例会開催予定:3月、6月、10月、12月の土曜日
-提携学会である韓国日本語教育学会より、発表と論文でのOPI特集を組んでいただけ
るとのご提案あり。5件(5名)の学会発表と論文投稿→9月に発表と論文投稿、学術誌掲載は12月。
→詳細は、別途MLにて募集をします。
14:30〜15:00 OPIデモンストレーション1
(テスター:今井先生、被験者:韓国人日本語学習者、大学生)
【インタビューの流れ】
故郷のチャンウォンについて(I)→専攻しているパーツデザインの設計に
ついて(A)→自動運転システムについて(S)→自動運転の危険性についての
意見(S)→今後、自動車はどのように発展していくか?(S)→ランニングに
ついて(I)→やせる以外の効果について(A/S)→ロールプレイ〈友達がSNS
に中傷を書いていたので、抗議してやめさせる〉(A)
15:00~15:30 3グループに分かれて議論(レベル判定、インタビューの仕方について)
15:30〜15:35 (休憩)
15:35〜15:55 各グループ発表
中級と上級の2つの結果に分かれた。それぞれの判定の主な理由は以下の通り。
中級-上
・しっかりした上級のタスク(叙述、比較)が少なかった。
・発話が文の羅列になっており、段落が構成されていない部分があった。
・発話内容が聞き手にとって理解しにくかった。
上級-下/中
・つっこんだ質問やナラティブ(語り)の質問がなかった。
・トリプルパンチの質問に対して被験者が逃げてしまう部分があった。
→超級×
また、インタビューの仕方に関するコメントも挙げられた。
・インタビューの全体の流れはとてもよかった。
・ウォーミングアップの時間をもう少し長くとり、様々な話題を集める
ようにするといいのではないか。
・被験者の意見をテスターがまとめてしまう部分が見られた。
《研究会としての判定(テスター保持者2名による判定)》
レベル:上級-中
判定理由:
・多数のコミュニカティブタスクを容易に自信をもってこなした。
・つながりのある段落の長さで、関連性のある事実を伝えられた。
・超級レベルをこなすときに、量と質の両方において発話レベル
が低下していた。
・超級タスクである仮説、反論に対する答えができていない。
→ほぼ超級=上級-上のところまでは達していない
15:55〜16:25 OPIデモンストレーション2
(テスター:鮱名先生、被験者:韓国人日本語学習者、会社員)
【インタビューの流れ】
家族、居住地のヨンインについて(I)→会社の業務内容(A)→会社での問題(S)
→イテウォンの事故について(A)→その際の警察の責任について(S)→安全に
関する個人の意識はどう変わるか(S)→映画「オジンオゲーム」について (A)
→ロールプレイ:運転免許の書き換えについて交渉(A)。
16:25~16:35 (休憩)
16:35~17:05 3グループに分かれて議論(レベル判定、インタビューの仕方について)
17:05~17:20 各グループ発表
中級と上級の2つの結果に分かれた。それぞれの判定の主な理由は以下の
通り。
中級-上
・叙述や描写の部分で挫折がみられた。
・段落が構成させていない部分、文の羅列があった。
・質問に対する答えがずれている部分があった。
・ロールプレイの内容が理解できていないようだった。
・韓国語由来の語彙を日本語で説明できていない部分があった。
→「ぎょうじ」、「ボキ」
上級-中
・発話量が多く、上級タスクもこなせていた。
インタビューのやり方についての意見
・インタビューの流れがスムーズでよかった。
・ 質問がスムーズにできていた。
《研究会としての判定(テスター保持者2名による判定)》
レベル:中級-上
判定理由
・中級レベルでの日常的によく起こるタスクや社交的場面を扱う際に
容易に自信を持ってやりとりができていた。
・かなりの数の上級タスクが遂行できていたが、できていない部分も
あった(映画のストーリー)→上級を維持していない。
17:45 終了
今回の定例会も、対面とオンラインの両方で開催しました。今回は日本語OPI研究会(東京)のケッチャム現会長と
世良前会長に出席していただき、一緒にOPIのレベル判定をしていただきました。そして今回の定例会のために、
小池先生、孫先生のご協力で2人の被験者に協力してもらうことができ、LIVEでのデモンストレーションを2件行う
ことができました。このような貴重な機会を作ることができたのも、両先生を始め会員の皆様のご協力で成り立って
いることに、改めて感謝いたします。
来年度(2023年度)は提携学会での学会発表や論文投稿といった研究の面でも力を注いでいく1年になると思いますが、
実際のOPIを実践したりレベル判定したりする機会もさらに増やしていきたいと考えています。来年度も皆様と一緒に
活動していければと思いますので、宜しくお願いいたします。
(文責:小島堅嗣/韓国OPI研究会会長)
Posted by J-OPI-K at
08:52
│Comments(0)